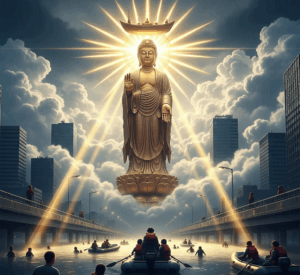【仏教ブログ】敬老の日、浄土真宗における老いについて
光顔寺明照廟堂/水月精舎(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、仏教アドバイザーの宮田秀成です。
9月の第3月曜日は「敬老の日」です。長い人生を歩んでこられた方々を敬い、感謝を表す日として定められています。地域や家庭でも、お年寄りを囲んで祝う行事が開かれ、世代を超えてつながりを確かめる大切な機会となっています。
仏教では「老い」を誰にも訪れる四つの苦しみの一つとして教えられます。四つの苦しみとは「生老病死」です。生きる苦しみ、病の苦しみ、老いる苦しみ、死ぬ苦しみを四苦と言われます。
一年生きれば、一年年を重ねるわけですから、老いるのは誰も避けられない事実です。それでも、アンチエイジングを心掛け、なるべく老いないように、歳はとっても若く見えるように努力される人も多くおられます。
この傾向は、以前より強くなり老いについてのマイナスイメージも強くなったのだと思います。「出来ることが出来なくなる」「人に頼らねばならない弱い存在」などです。
確かに人間は肉体的には成人年齢をピークに下降線をたどります。スポーツ選手でも、学問の世界でもピーク年齢を超えるとあとは下り坂ということは多いです。
しかし、浄土真宗では、歳をとることは衰えではありません。それが「お育て」と言うものです。
「お育て」とは、阿弥陀仏が私に向かって絶えず念仏する身となるように、念仏する身となり浄土に往生する身となっても、念仏者として育てていかれることを言います。
そういう意味では、念仏者はいつまでもお育てによって成長を続ける身ということになります。
以前は、お聖教や法話で今一つわからなかったところが、有り難いと思わせていただけるのは、阿弥陀仏のお育てのおかげです。
肉体的には、衰えるばかりですが、お育てによって成長を続けられるという点で、歳をとることもまた、ありがたいご縁となります。
この敬老の日に、老いも有り難いご縁となる身にてならせていただきましょう。

※上の画像は生成AIが考えた「老いを迎えて、美容外科で施術にクレームをつける人と、お寺の本堂の阿弥陀如来の前でお聖教を拝読する人」です。
ーーーーーーーーー
Profile
1993年に宗教法人浄土真宗親鸞会に入信、10年間親鸞会講師として活動。
脱会後、親鸞会の教えの誤りに気づき、本願寺派の教えを中心に学びなおす。
現在、浄土真宗本願寺派光顔寺信徒。
光顔寺スタッフ。仏教アドバイザー。