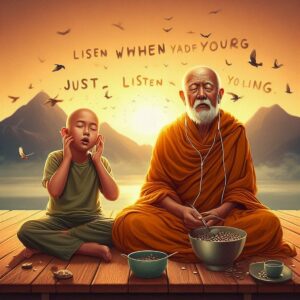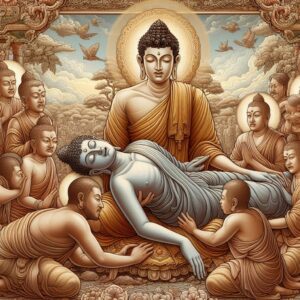【仏教ブログ】道路陥没事故から下水管と死を考える
光顔寺明照廟堂/水月精舎(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、仏教アドバイザーの宮田秀成です。
2025年1月28日、埼玉県八潮市の県道交差点で道路が陥没し、直径約5メートル、深さ約10メートルの穴が開き、トラック一台が落下しました。その後、近くにも穴が開き、幅は最大40メートルにまで拡大しました。
連日報道をされていますが、原因は地下に埋めてある下水道管が腐食したことによるものとされています。報道によれば、小さい陥没も含めると昨年だけで二千件以上起きているとのことでした。コンクリート製の下水管の耐用年数は50年といわれ、今後20年で同様のケースは増えるとも言われています。
そんな下水管は、日本全体では総延長49万キロメートルにも及ぶといいます。私たちが生活している道路のかなりの部分に下水管がはりめぐらされていることになります。
土で覆い隠されていますが、気がつけば足下に穴が開いているというのは、人の生と死の関係によく似ていると思います。臭いものに蓋ではありませんが、下水は人目につかない場所を通って処理されています。できれば関わらずにしたいというのが人情ですが、見ないようにしたところで、それを抜きにまた生きることはできないものです。
実際に、道路陥没が起きた地域では、洗濯や風呂を控えるようによびかけられています。日頃意識はしていなくても、いざとなるとそれを抜きには生きていけないのが下水管です。
生きている私にとって、死というのは忘れて生きていても、避けて通ることができないものです。しかし、下水管のようにいたるところにあり、今回の事故のようにいつかは向き合わねばならないものです。
呼吸のあひだにすなはちこれ来生なり。(教行信証・行文類より)
といわれます。
日頃何気なく呼吸をしている間にも、この生が終わって次の生になる時が必ず来ます。「滅多なことはないだろう」と日頃思っていても、その「滅多なこと」は呼吸の間につねに触れ合っています。
生きているときに、必ず死なねばならない問題は解決しなければなりません。これを蓮如上人は「後生の一大事」と御文章に書かれています。それを浄土真宗では教えられていますので、法座のご縁があればお参り下さい。
※下の画像は生成AIが考えた「阿弥陀如来を前に後生の一大事を聞く人々」です。

ーーーーーーーーー
Profile
1993年に宗教法人浄土真宗親鸞会に入信、10年間親鸞会講師として活動。
脱会後、親鸞会の教えの誤りに気づき、本願寺派の教えを中心に学びなおす。
現在、浄土真宗本願寺派光顔寺信徒。
光顔寺スタッフ。仏教アドバイザー。